こんにちは、macaronです。
今回はSFといえばコレ!と言われている小説、「星を継ぐもの」の感想です。
ド文系人間のため、物理学や化学・科学、生物学の深いところどころか、初歩すら理解出来ていないですが、物語の壮大な結末に、読む手が止まりませんでした。
いきなりこんな本格的なの大丈夫かな……?と思っていましたが、杞憂でしたね。
以下よりネタバレ有りの感想になります。
それでは、どうぞ!
登場人物 & あらすじ
登場人物
・ヴィクター・ハント:原子物理学者
・クリスチャン・ダンチェッカー:生物学者
・グレッグ・コールドウェル:国連宇宙軍本部長
・チャーリー:月面で発見された遺体。5万年前に亡くなっている。
あらすじ
月面調査隊が深紅の宇宙服をまとった死体を発見した。すぐさま地球の研究室で綿密な調査が行われた結果、驚くべき事実が明らかになった。死体はどの月面基地の所属でもなく、世界のいかなる人間でもない。ほとんど現代人と同じ生物であるにもかかわらず、五万年以上も前に死んでいたのだ。謎は謎を呼び、一つの疑問が解決すると、何倍もの疑問が生まれてくる。やがて木星の衛星ガニメデで地球のものではない宇宙船の残骸が発見されたが……。ハードSFの新星ジェイムズ・P・ホーガンの話題の出世作。
ジェイムズ・P・ボーガン「星を継ぐもの」 あらすじ
感想
未知の答えに辿り着く
冒頭でも書いた通り、SFを読むのはこれが初めてです。
(カミセン主演の映画「COSMIC RESCUE」を見たことがあるくらいです。)
しかも完全な文系人間のため、「生物学における進化とは~」とか「体重から重力が~」とか書いている部分はほとんど理解出来ていません!笑
それでも、チャーリーという「月で5万年前に死んだ、我々地球人とほぼ同じ構造を持つ生物」について、各方面から考察が飛び交っているシーンはずっとドキドキして、ページを捲る手が止まらなかった。
物理学、生物学、数学、化学、科学、地学、言語学……それぞれの専門家が集まって、それぞれの見識から意見を述べる、そして分からないところはまた別分野の専門家がフォローする。
こういう天才vs天才(今回は協力関係ですが)みたいな構図、大好きです。
そして何より、人類はこうやって進化を遂げてきたのだな……と、この本自体がその縮図みたいに感じられました。
最初は狩猟民族から始まって、火の発見、食料保存、移動手段、通信手段、そして武器。
決して良い方面ばかりではないし、それが今の環境問題に繋がっているという側面もあるのだけれど。
それでも、その時の最新の知識と技術を持ち寄って技術を発展させてきた歴史って、こういう未知への好奇心と考察と、果てしなく緻密で地道な実験から作られてきたんだろうな、となんだか壮大な所まで考えてしまいました。
ちなみに、当初の「こうじゃないかな……?」が二転三転しているのは、更に好きです。
一旦、誰もが反論できない回答に辿り着いた主人公のハント博士が、それを発表した途端に別方面から更に圧倒的回答がぶつけられるあの展開。
私は鳥肌がしばらく治まらなかったので、ぜひ体験してみて欲しいです。
ネアンダルタール人の滅んだ謎と、「星を継ぐもの」というタイトル回収が一気に押し寄せてきます。
そこからのエピローグは思わず「勝負、勝ったんだね……!」と涙を流しました。
人間関係が変わる瞬間
あのね、ハントとダンチェッカーの関係が変わる瞬間、めちゃくちゃ良くないですか??
読んだ人はほとんどの方が思ったはず!!!どうでしょう?
何でしょう、あの少年漫画によくある(?)いつも喧嘩ばかりしているライバル同士が、いつの間にか雪解けしていて、目的のために協力し合う展開。
要するに、ダンチェッカーの何もかもが気に入らないのだ。ダンチェッカーは痩せすぎている。着ている服はあまりにも古めかしい。その服をダンチェッカーは、まるで洗濯物を干しでもするかのようにまとっている。時代遅れな金縁眼鏡は笑止千万だ。もったいぶった丁寧な話し方は不愉快である。彼ははたして、生まれてこのかた笑ったことが一度でもあるだろうか。干からびた皮膚で真空パックされた頭……。ハントはそんなことを考えていた。
ジェイムズ・P・ボーガン「星を継ぐもの」 p87-88
「わたしは遠慮します、ハント先生」彼は静かに言った。
ハントは溜息をついて行きかけた。
「もっとも……」ダンチェッカーの声の様子にハントはつと足を止めて振り返った。「あなたの新陳代謝が不慣れな非アルコール系飲料のショックに耐えられるようでしたら、濃いコーヒーなら、その、大歓迎ですが」
冗談だった。何とダンチェッカーは自分から冗談を言ったのだ。
「何でも一度は試ししてみる主義でね」エレベーターに向かいながら、ハントは言った。
ジェイムズ・P・ボーガン「星を継ぐもの」 p232-234
上二つは、物語前半と佳境に入るくらいの場面の引用ですが、同じ人を描いているのかと思うほど違って見えますよね。
そして最終局面で意見がぶつかり合うのも、この二人というのがとても良い。
主人公のハントは、最初は全然別の人と行動を共にしているんですよね。(彼が当初所属している会社のロブ・グレイという人)
だからなんとなく、この物語を引っ張っていくのはこの二人なのかな~と思っていたのですが、全然違う角度からパートナーというか、主となって議論していく人が飛び込んで来て驚きました。
まあでも思い返してみれば、そもそも当初毛嫌いしているのが印象としてはかなり残るし、コールドウェルの台詞とか、態度とかに示されていたので、それに気付く場面はたくさんありましたね……。
それにしても、チャーリーの不明点解決に向けてはこの二人に協力して貰うのが一番!と思って、そう仕向けたコールドウェル氏の手腕は凄かった。
全部この人の手のひらの上で転がされていたというか……最強じゃん、コールドウェル。
そして、そう仕組もうとしていたコールドウェルに違和感を抱きながら、最後合点がいったときにハントが彼に素直に向き合うのがまた素敵。
これまで来るもの拒まず、去るもの追わず……そして通り過ぎた過去は振り返らず、常に今と未来だけを見て生きてきたハントが、チャーリーの件を通して、わずかだけど自分を取り巻くものに対する捉え方が変化していて。
問題を解決する事だけじゃなく、それを通して起こる別の変化みたいなものにも、とても心を奪われる作品でもあったな。
終わりに
5万年前に亡くなったチャーリーの手記から、少し引用します。
ミネルヴァはどうなったろうか。この禍いの後、はたしてわれわれの子孫はより恵まれた場所で生き延びるだろうか。もし生き延びたとしたら、彼はわれわれが何をしたか、いくらかでも理解するだろうか。
しかし、この宇宙のどこかに、温かく、色と光に満ちた世界があるならば、われわれがしてきたとこから、何か意味のある結果が生まれるはずなのだ。
ジェイムズ・P・ボーガン「星を継ぐもの」 p216
「星を継ぐもの」というタイトル。
本編ラスト~エピローグで最高に盛り上がるのですが、個人的にはこのチャーリーの手記がそれの起爆剤になっているように思います。
「色と光に満ちた世界」とはまさに地球が当てはまるね、となるのですが、事情はあれどそんな世界でも争いはずっと続いている。
彼らが夢見た世界というのは、ずっと続くことはないだろう今の文明が滅びるまでの間に、いつか実現することが可能なのかな。
これまで歩んできた過去の事、まだ見ぬ未来のこと、そしてまさに私たちが生きている今このときのこと。
いろんな瞬間に思いを馳せて、考え込みたくなる小説でした。
続編があるようなので、読んだらまた感想共有出来ればと思います。
それでは!
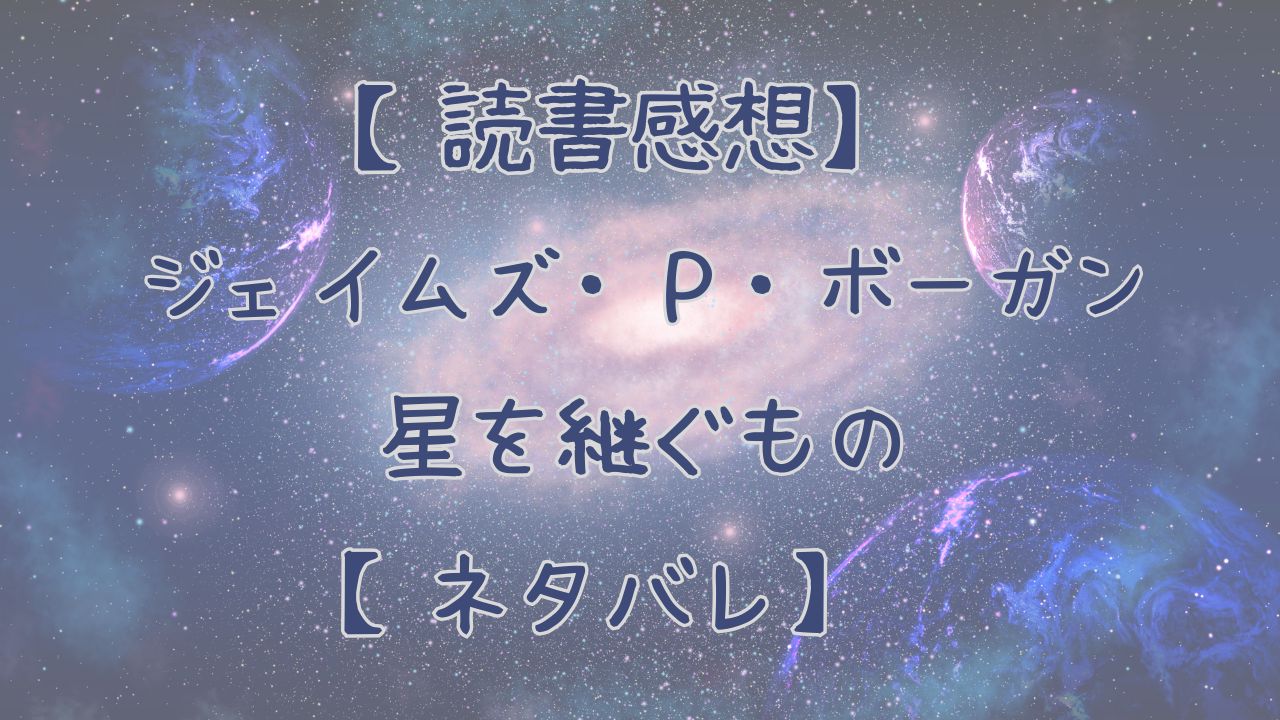
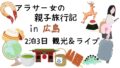

コメント